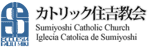2月9日 年間第5主日
黙想のヒント
「先生、私たちは夜通し苦労しましたが、何もとれませんでした。しかし、お言葉ですから、網を降ろしてみましょう」(ルカ 5:5)
このペトロの言葉は私たちの日頃の叫びです。「今まで努力したけど何の成果もなかった。もうやめようかと思う」など。しかし大事なのは「お言葉ですから、網を降ろしてみましょう」即ち、「あと1回チャレンジしてみよう」という心構えです。絶望と希望、失敗と成功は表裏一体で、どちらかであり続けることはないのです。「逆境にある人は常に『もう少しだ』と言って進むといい。やがて必ず前途に光が差してくる」(新戸部稲造)
人間は失敗からこそ多くのことを学びます。反対に「成功は最低の教師だ。優秀な人間をたぶらかして、失敗などありえないと思い込ませてしまう」(ビル・ゲイツ)のです。場合によったら見方を変えて、「この失敗のよかった面は何だろうか」と失敗を逆手に取ることも大切です。失敗は生き物であり、失敗の中にこそ成功の種があるからです。また努力が足りないのではなく、方法が間違っていたのではないかと問いただすことも必要です。登山ルートは1か所とは限りません。東西南北から登れます。即ち、自分が見方を変えることによって、新しい可能性はいくらでも開けます。「何も咲かない寒い日は、下へ下へと根を伸ばせ。やがて大きな花が咲く」(マラソンランナー高橋尚子の座右の銘)
発明家トーマス・エディソンはまたユーモアの人でもありました。彼は実験に1万回失敗しても、「私は失敗したことがない、ただ1万通りのうまくいかない方法を見つけただけだ」と言い、失敗にもユーモアで意味を与えました。失敗しても、そこから何か新しいことを学んだら、それはもはや失敗ではなく「貴重な体験」になるのです。失敗は希望を生み、希望は新たな勇気を生みます。「富を失う者は多くを失う。友を失う者はさらに多くを失う。しかし勇気を失う者は全てを失う」(セルバンテス)
ところで別の見方もあります。私たちが人生で直面する多くの問題は、実は心で解決されることが多いのです。一休和尚こと一休宗純は亡くなる前、遺言状を弟子に託して、「この遺言状は将来、この寺に大きな問題があったときにのみ開け。それまでは絶対読むな」と命じました。その教えは代々守られ、決して開かれることはありませんでした。その遺言状が開かれたのは死後100年を経過してからです。解決策を期待して開かれた遺言状には、「なるようになる、心配するな」と一言。一瞬拍子抜けになりながらも、心を前向きにさせる力がこの言葉にはあります。問題だからと言って慌てていては、解決するものも解決しないからです。起こった問題よりも、それに舞い上がり感情的になっている心こそが実は問題なのです。私たちも思い当たる節が多いかと思います。
(寄稿 赤波江 豊 神父)