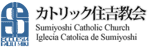4月6日 四旬節第5主日
黙想のヒント
「イエスはかがみ込み、指で地面に何か書き始められた」(ヨハネ8:6)
律法学者たちやファリサイ派の人々が、姦通の現場で捕らえられた女を連れてきて、イエスを試そうとして議論を吹きかけます。「こういう女は石で打ち殺せと、モーセは律法の中で命じています。ところで、あなたはどうお考えになりますか」(ヨハネ8:5)しかし、その時のイエスの態度が不可解です。なぜイエスは彼らと議論しなかったのでしょうか。実は、イエスは彼らと議論すれば、この女性をますます苦しめることを知っていたのです。彼女の姿を想像してみましょう。今、彼女は今恥ずかしさと恐怖でうつむき、顔は青ざめ、震えあがっています。イエスは彼女の苦しみを激しく感じ取り、うつむいている彼女に合わせ、自分もかがみ込みます。かがみ込むということは、イエスは彼女の顔を見ないということです。ここに、弱い立場の女性に対するイエスの深い思いやりを見ることができます。この時イエスが彼らと議論すれば、彼女の顔を見ることになり、ますます彼女に恥ずかしい思いをさせることになるからです。
しかし、執拗に問い続ける彼らにイエスは身を起して言います。「あなたたちの中で罪を犯したことのない者が、まず、この女に石を投げなさい」(8:7)そして再び身をかがめます。イエスの言葉に対して、年長者から始まって、一人また一人と立ち去ってしまい、ついに誰もいなくなり、そこにいるのはイエスと彼女だけです。そのとき、イエスは身を起して彼女の顔を見ながら言います。「婦人よ、あの人たちはどこにいるのか。誰もあなたを罪に定めなかったのか」(8:10)そして女性も初めて口を開きました。しかし、それは自分の罪に対する反省や謝罪の言葉ではなく、わずか一言「主よ、誰も」(8:11)だけで、それ以上の言葉を言う力はなかったのでした。しかしイエスもそれ以上の言葉は求めません。そして最後に言います。「わたしもあなたを罪に定めない。行きなさい。これからは、もう罪を犯してはならない」(8:11)
その後うつむき、憔悴しきった表情でイエスのもとを去った彼女と、人生で深く傷ついた人たちに、19世紀のアメリカの詩人ロングフェローは語りかけています。
「悲しげな歌を聴かせないでくれ。人生は虚しい夢ではないのだ。眠っている魂にとっては虚しい夢かもしれないが、目覚めた魂にとって人生は現実そのものである。その人生の成否を決めるものは、その人の心の中に情熱が燃えているかどうかである。あなたの心臓は絶えず死に向かって葬送行進曲を打ち鳴らしている。だからと言って、あなたは屠り場に引かれていく家畜のようであってはならない。あなたは人生の英雄であれ、戦うのだ。 時の砂上に足跡を記せ。それは時間とともに波が消してしまうかもしれないが、あなたと同じように人生の大海原で難破して傷ついた人が、それを見てもう一度生きる勇気を奮い立たせるような足跡を。そのためにあなたは生きているのだ」(『人生の詩編』)
(寄稿 赤波江 豊 神父)