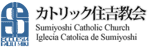5月11日 復活節第4主日
黙想のヒント
「わたしの羊はわたしの声を聞き分ける」(ヨハネ10:27)
羊である私たちがイエスの声を聞き分けるためには、それなりの心構えが必要です。それは聞いて何かを決断するためです。人生は決断の連続です。私たちは常に多くの選択肢の中から何らかの決断を求められ、そこから枝分かれしながら、前へ前へと進んで行きます。決断は人間の進歩を促す強力な力です。人生の中に大きな決断を持ち込まない限り、人間は成長することはできません。しかし決断には迷いがつきものです。決断できず、いつまでも迷ってしまうケースもあります。しかし、「長く考え込んでいるものが、常に最善の選択となるわけではない」(ゲーテ)のです。
中国史上最高の名君の一人とされる唐の太宗が、重要な決断を誤らないために大切にしていたのが「三鏡」です。『それ銅をもって鏡となせば、もって衣冠を正すべし。古をもって鏡となせば、興替(国の行く末)を知るべし。人をもって鏡となせば、もって得失を明らかにすべし。朕常にこの三鏡を保ち、もって己の過ちを防ぐ』つまり「銅」とは昔の銅鏡のことで、鏡に映し出される自分の精神状態を管理することです。即ち、正しい決断のためには、正しい精神状態を維持することがまず必要で、このことはロヨラのイグナチオも『霊操』の中で不安、怒り、パニックなど、心が嵐の時は決して重大な決断をしてはいけない、必ず後悔すると語っています。二つ目は「古」で歴史のことです。人間の世界に生起することは、過去に起こった出来事の繰り返しに過ぎないので、何かの決断に際してそこから類推して大切なヒントを得ることができます。三つ目の「人」とは、自分の傍にいて、「あなたは間違っている」と率直に進言してくれる人のことです。私たちは自分の考えだけで走ってしまえば、多くの場合間違えてしまいます。情熱という名の思い込みで周りが見えなくなるからです。心の管理と歴史に学ぶ姿勢、そして誤りを指摘してくれる友人の存在、これは「イエスの声を聞き分ける」ためにも必要な心構えなのです。
時として、悩んでも、悩んでも決断できない時があれば、それは結局「どちらでもいい」レベルなのです。聖書にいいヒントがあります。イスカリオテのユダに代わって、新たに使徒を選ぶとき、人々はマティアとユストを候補に挙げ「次のように祈った。『全ての人の心をご存じである主よ、この二人の内のどちらをお選びになったかを、お示しください。ユダが自分の行くべき所に行くために離れてしまった、この使徒としての任務を継がせるためです』二人のことでくじを引くと、マティアに当たったので、この人が十一人の使徒の仲間に加えられることになった」(使徒言行録1:24~26)大切な使徒をくじで選ぶとは何事かと思うかも知れませんが、本当はマティアでもユストでもどちらでもよく、大切なのは「結果の中に神のみ旨を見る」ことなのです。即ち、自分が選んだことをしっかり果たすこと、これが神のみ旨です。人生は決断の連続です。しかし、「過ぎて帰らぬ不幸を悔やむのは、更に不幸を招く近道である」(シェークスピア)
(寄稿 赤波江 豊 神父)