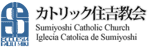8月17日年間第20主日
黙想のヒント(第265話)
「あなたがたは、わたしが地上に平和をもたらすために来たと思うのか。そうではない、言っておくが、むしろ分裂だ」(ルカ12:51)
今日の福音は、愛を強調したイエスの言葉と一見矛盾するかのような過激な言葉です。しかし、これには当時の時代背景を考慮する必要があります。イエスの在世当時イスラエルはローマ帝国の支配下にありましたが、紀元前27年の皇帝アウグストゥスの即位から紀元180年の皇帝マルクス・アウレリウスの死去までの約200年間戦争はなく、人々はこの時代を 「ローマの平和」と呼んでいました。しかしこれは帝国内で戦争がなかっただけで、多くの奴隷の犠牲の上に一部の特権階級による富の独占、モラルの低下など見せかけの平和であったのです。イエスの登場は、このような偽りの平和に対する挑戦状でした。今日の福音は、イエスのように純粋な愛に徹して生きれば、周囲との衝突や分裂、迫害は避けられないことを意味しています。
歴史の中でイエスのように純粋な愛を説いたため迫害された人は多く、イエス以前にも中国で他者への無条件な愛を説いた墨子(BC470頃~BC390頃)がいました。当時の中国は孔子を祖とする儒教を信じていました。儒教は「仁愛」を基礎とし、また身分社会の存在を前提にしていました。また祖先と親を尊敬し、家族を大切にすることを第一に挙げるのですが、その反面他者へ愛などはおろそかになりがちでした。
墨子はこの儒教を徹底的に批判しました。彼は、人は男も女も、貧者も弱者も皆平等に尊重されねばならないと、儒教の仁愛に対して「兼愛」を主張しました。また一人の人間が殺人を犯せば罰せられるのに、一国の君主が他国を侵略して大勢の人を殺しても罰せられず、反対に祖国に栄誉をもたらしたと称賛される。しかしこれは愛を失った弾劾されるべき行為である。敵国への愛を重んじて憎しみを捨てよ。そこに平和がある。では攻め込まれたらどうするのか。その場合は守り抜く「非攻」という考えを主張しました。また盛大な葬儀などの贅沢を否定し、生活においても習慣においても節約を説きました。
しかし戦国の世が秦の始皇帝によって統一されたとき、墨子の教団は姿を消してしまいました。墨子の思想は、儒教を中心とした当時の社会にとって過激な反体制理論であり、許されるべきではないというのがその理由であったと思われます。
墨子の教えは他者への無条件の愛など、現代のヒューマニズム(人道主義)にも匹敵し、イエスの教えに通じるものがあります。イエスもローマ帝国支配下のユダヤ社会で墨子と同じように危険分子とみなされ、十字架上で処刑されました。それによってイエスの存在は一度消滅したかのように見えましたが、弟子たちによって受け継がれ、キリスト教は多くの迫害を受けながらも生き続けました。後にローマ帝国の国教となって世界的な広がりを見せたのは、単に倫理的な教えだけにとどまらない復活信仰の力でした。
(寄稿 赤波江 豊 神父)