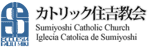8月24日年間第21主日
黙想のヒント(第266話)
「わが子よ、主の鍛錬を軽んじてはいけない。主から懲らしめられても、力を落としてはいけない。なぜなら、主は愛する者を鍛え、子として受け入れる者を皆、鞭打たれるからである」(ヘブライ人への手紙12:5~6)
自分の人生を振り返って、この聖書の言葉を実感する人は多いと思います。しかし世の中には、この言葉だけでは表現しきれない壮絶な闘いの末、人生の意味に到達し、多くの人に勇気を与えた人は多くいます。『苦悩を突き抜けて歓喜に至れ』これは楽聖と称えられ、数々の名曲を世にもたらしたルートウィヒ・ヴァン・ベートーヴェン(1770~1827)の生涯を表す言葉です。しかし彼の人生は壮絶そのものでした。宮廷楽団のテノール歌手だった父親はアルコール依存症で生活は困窮し、彼の才能を見出した父親は彼に一家を託そうと、日夜過酷なスパルタ教育を施しました。母親は精神的な病を負い、祖母もアルコール依存症で入院先の病院で亡くなりました。彼自身も幼少期から精神的に不安定で不器用、さらに性格的にも暗く、近所の少年たちから馬鹿にされていました。
家庭の不幸、自身の精神的病、さらに音楽家として致命的な病を負うことになります。病気で20代後半から極度の難聴に陥ってしまったのでした。精神的にも追いつめられ、一時は自殺も考えましたがそれでも踏みとどまり、「私を引き留めたのは芸術だった。自分が使命を感じている仕事を成し遂げないで、この世を見捨ててはいけないように思われたのだ」と書き残しています。彼は様々な不幸、絶望的とも言える極度の難聴という苦境の中で使命を果たす覚悟を決め、一曲また一曲と名曲を創り上げていきます。
当時ヨーロッパ全域で専制君主制が復活し、オーストリアの宰相メッテルニヒは反体制派を弾圧する恐怖政治を強行したのでした。これに対抗するように、ベートーヴェンは合唱によって自由を謳歌する「歓喜の歌」を挿入した第九交響曲を書き上げました。友人のエルデーディ夫人に「私たちはひたすら悩むため、そして歓喜するために生まれついているのです。最善なのは苦悩を突き抜けて歓喜に至ることです」と書き送っています。
音楽的にも、思想的にもベートーヴェンの集大成となった第九交響曲を、自ら初めてウィーンのケルントナートール劇場で指揮して演奏したのは、死のわずか3年前でした。演奏後、満場の聴衆は熱狂して、割れんばかりの大喝采、大拍手をベートーヴェンにおくりました。興奮した聴衆はアンコールを繰り返し、5度目にやっと警官によって制止されたと伝えられます。しかし客席に背を向けて指揮していた難聴の彼には、何が起こっているのか分かりませんでした。側にいたアルト歌手が彼の手をとって聴衆の方に向かわせ、初めて歓喜にあふれた聴衆の顔を見て、第九交響曲が成功したことを知ったのでした。
喜びと悲しみは表裏一体です。悲しみを排除して喜びだけを求めることはできません。悲しみ経てこそ喜びに至ります。喜びだけではなく、悲しみに対しても「悲しみよ、ありがとう」と言いましょう。
(寄稿 赤波江 豊 神父)