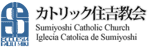8月31日年間第22主日
黙想のヒント(第267話)
「賢者の心は、格言を思いめぐらし、知者の耳は、格言を熱心に聴く」(シラ書3:29)
私たちは情報化社会という言葉の氾濫の中で生きています。しかし実際耳にする言葉の多くは右から左へと聞き流され、忘れられていきます。しかし何か大きな出来事の中で出会った言葉によって心を揺り動かされ、人生が変わることを経験した人は少なくありません。人間が極限状態にあり、また何か真剣に取り組んでいるときに発した言葉は、誰の心をも打ちます。それがどのようなものであれ、偽りなく真理を含んでいるからです。
長い歴史を通して、多くの人々の知恵によって研ぎ澄まされた短い格言や名言には思わず目を引くものがあります。その言葉には、その言葉を発した人の全人格と全人生が集約されているからです。同時に格言や名言が長い歴史を通して人の心に訴え続けているのは、実は「人はいつの時代でも同じことで悩んでいる」ことを示しています。
同じ言葉に出会っても、その人の置かれた状況によって受け取り方も様々です。その言葉を残した人がどのような意味を込めて語ったとしても、聞く人、読む人はそのときの心のあり方によって自分なりに受け止め、かみくだき、消化しながら自分なりに意味付けをしていきます。それでいいのです。
生きる力の原動力は希望であり、その希望を支えるのが言葉です。現在多くの人が心の問題で悩み苦しんでいますが、その原因は決してストレスだけではなく、精神という土台が脆弱なうえに、心が過度な負担を強いられているからです。心の骨格は精神で成り立ち、精神は言葉で表現されます。
以前日本の教育では、丸暗記が低いレベルに置かれていたことがありました。しかし昔の日本で論語などの暗唱が盛んに行われていた時代には、日本人の心もしっかり安定していました。論語が日本人の精神を構築し、支えていたからでした。例えば吉田松陰や夏目漱石は、子どもの頃から論語を暗唱することで自分の体に言葉を刻み込んでいました。こうして彼らの身に蓄積された言葉はやがて自分の名言となり、心の骨格、行動の指針となり人生を支えたのでした。このことは昔子どもの頃、長崎でカトリック要理や祈祷書を丸暗記させられた信徒の精神の強さからも理解できます。
格言や名言、ことわざなどは世界中無数にあります。それら全ては人生について語り、生きようとする人全てに何らかの示唆を与え、いつの時代でも新鮮で、感動的な響きをもっています。情報が氾濫し、フェイクニュースが身を脅かす時代にあって何が正しいかを識別する手段が、「価値あるものは残る」という見方です。長い歴史を通して人間の心を支えた格言や名言、諺などそれなりの価値があり、今一度見直す必要があります。
私たちにとって「価値あるものは残る」の代表は聖書です。「人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生きる」(マタイ4:4)しかし人を生かす全ての格言名言も、神の口から出る言葉と言っても過言ではありません。
(寄稿 赤波江 豊 神父)