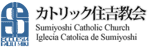9月14日十字架称賛
黙想のヒント(第269話)
「モーセが荒れ野で蛇を上げたように、人の子も上げられねばならない」(ヨハネ3:14)
私たちはイエスの十字架の傷によって救われ、癒されました。十字架称賛の祝日はこのイエスの十字架に感謝するだけではなく、私たちもまたそれぞれの過去の十字架を思い、それに感謝し称賛する日です。なぜなら過去の十字架は私たちを傷つけたが、その十字架によって人生の意味を知り、信仰が強められたからです。ですから私たちは過去にどんな辛いことがあったとしても、それを等身大で受け止め、そこに意味を見出し、それをステップとしてさらに生き続けなければならないのです。その意味で決して人生にNoと言ってはならず、常にYesと言いましょう。「絶望は人生に必ずつきまとうものだ。絶望しないような人間はある意味で頼りない人だといえる。なぜなら小さな自己に満足し、なんらの努力も考えごともしない人に、絶望は起こりえないからだ」(亀井勝一郎)
『善の研究』で知られる哲学者西田幾多郎は、ある日6歳の二女を亡くしました。それまで可愛がって、一緒に遊び歌っていた娘が突然消えて、白い骨になってしまったとはどういうことか。彼はこのことが受け入れられず、いつか時の流れが解決してくれると思っていました。しかしそれでも癒されず、ああしてやればよかった、こうしてやればよかったと、ただ後悔の念ばかりが彼を襲います。しかしやがて彼は、この苦しみは自力にばかり頼っていた結果だと悟ります。娘が亡くなったことは運命であり、他力という大いなる力に身を委ねることで、彼は心の重荷を降ろすことができました。自力で学問の道を切り開いてきたこの偉大な哲学者が、乗り越えられない悲しみに直面したとき、この他力という考えによって自分を保つことができたのでした。
私たちには、自力で頑張って生きなければならないという拘束感から解放され、この他力、即ち神によって生かされているという安心感が必要です。「私は生かされている。野の草と同じである。路傍の小石と同じである。生かされているという宿命の中で、精一杯生きたいと思っている。精一杯生きるということは難しいことだが、生かされているという認識によって、いくらか救われる」(東山魁夷)この生かされているという認識こそ、苦しみに意味を与え、また人への感謝の念を生み出すのです。反対に、過度に真面目で責任感が強すぎると、自力主義の蟻地獄に陥りやすく、人への感謝の念も薄くなりがちです。
申命記が述べるように、蛇は罪と死のシンボルであり、人々は蛇によって一度死にましたが、悔い改めて青銅の蛇を仰ぐことによって再び命を得ました。即ち、私たちは過去の十字架によって一度死にましたが、その十字架をもう一度仰ぎ見て、そこに意味を見出すことによって、新たな生命の光にふれます。そのためには、今一度肩の力を抜いて、今まで生かしていただいた。今日も生かされている。これからも生かしていただける。この思いで周囲の人たちに感謝をささげ、大いなるお方、即ち神の導きに身をゆだねましょう。
(寄稿 赤波江 豊 神父)