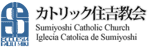10月12日年間第28主日
黙想のヒント(第273話)
「イエス様、先生、どうか私たちを憐れんでください」(ルカ17:13)
こう叫んだ10人の重い皮膚病の人たちは、昔ライ病とかハンセン病とか言われ、当時のユダヤ社会では罪人とされて人々との接触が禁止されていました。また病気は罪の結果であり、ファリサイ派や権力者たちによれば彼らは異邦人と同様救いから除外されていました。イエスは当時のユダヤ社会にあって、ファリサイ派や権力者たちとも関わりながらも、真の神の掟を守るため彼らと対立し、逆らいのしるしとなったのでした。
江戸時代後期に二宮尊徳(金次郎)という農政家、思想家がいました。二宮尊徳と言えば、背中に薪を背負って読書している勤勉な少年の像で有名で、昔の小学校などによくその銅像があったものです。ある日、田植えが終わったばかりの村で彼がナスの漬物を食べたところ、これは秋ナスの味がすると言い、間もなく冬が来ると言ったのでした。田植えが終わったのは初夏でこれから夏を迎えるのに、彼は冬の到来を予告しました。そして大変な形相で田植えが終わったばかりの稲の苗を全部抜くように命じ、寒さに弱い米ではなく、寒さに強い稗(ひえ)を植えるように命じました。実際その年は冷夏で、その年から日本中が地獄絵図となった「天保の大飢饉」が始まったのでした。しかし彼の村からは一人の餓死者も出ず、余分な稗を近くの村に配るなどしました。彼は冷夏を否定せず、冷夏に強い稗を植えるなどして冷夏に逆らい、冷夏を利用したのでした。
その二宮尊徳が人間とは何かを考える際によく使ったのが「水車の例え」でした。水車の下半分は水の流れ、つまり天(自然)の力に従わなければ回りませんが、上半分はその流れに逆らわなければ水車はその用を足しません。つまり水車は半分天に従い、半分天に逆らうことで水車としての使命を果たします。天保の大飢饉で人々が天に逆らって生きていく力を失った時代だからこそ、尊徳は天に逆らうことの意味を強調したのでした。
つまり「水車の例え」は、自分自身が水車で、直面している現実や人が川です。水車は川に飛び込んで回り始めますが、水に流されてしまうのではなく、その場にとどまり川とは逆向きに動く。つまりどんな現実でも相手でも一旦受け入れるが、正しく生きるためには自分の意志で逆らう。どんな現実でも実りを生む力を持っているからです。水車と川、つまり個性の違うものが相互にエネルギーを出し合い、豊かな実りをもたらすのです。
尊徳は「自分自身のものさしを持たない」ことを強調しました。つまりこの時、この状況を当たり前とは思わず、今普通に生きているこの瞬間を注意深く観察し、何が起ころうとしているか常に知るように諭したのです。この「自分自身のものさしを持たない」ことをパウロは次の言葉で表現しています「私たちは、キリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きるようになる」(Ⅱテモテ2:11)つまり自分自身をものさし、基準にするのではなく、キリストを基準にすることです。「私たちが誠実でなくても、キリストは常に真実であられる」(同2:13)からです。
(寄稿 赤波江 豊 神父)